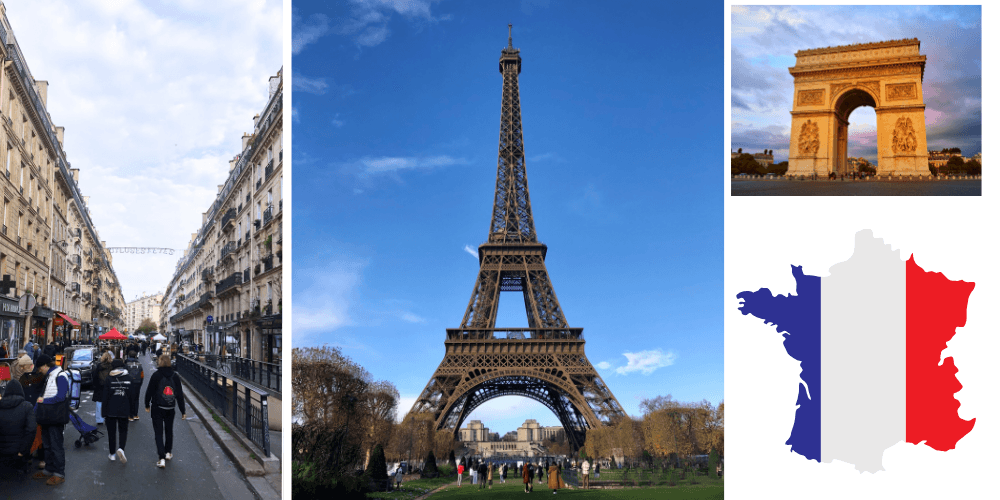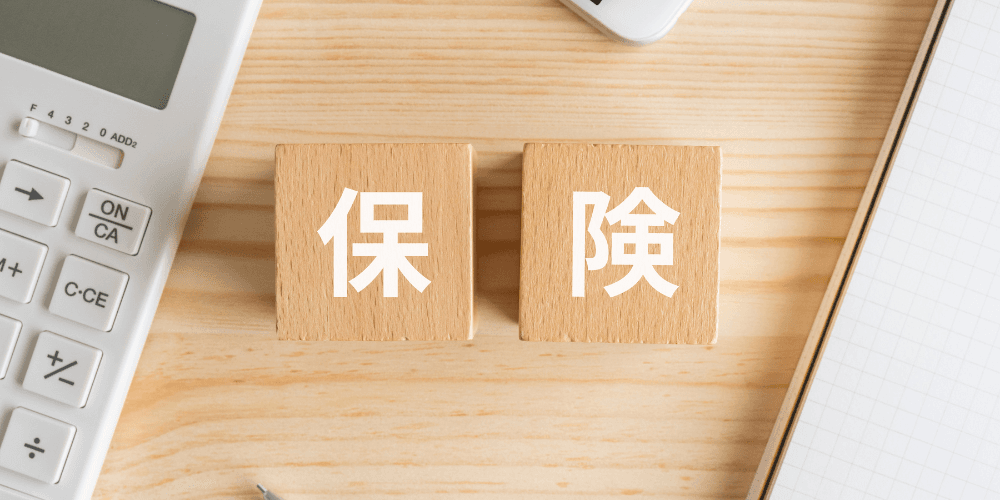マンション管理費等を払えない人は必ずいる!?

今回は、管理費等の督促支援・補助業務とその関連事業に25年間従事しているマンション会計部 収納課 収納サポートチーム 福原悟さんを取材した。
「督促」というと、管理費等の滞納者に対して「管理費を支払ってください」と電話をする業務、と単純に考えがちだが、実はそうではない。なぜ滞納するようになったのか、本人に支払い能力がない場合にどうしたらよいのか、知識と経験がないと対応できない。
◆取材者:久保 依子 マンションみらい価値研究所 所長

昨今では、管理費等の滞納と、高齢化の問題を切り離して語ることはできない。区分所有者の意思能力が認知症などで衰えれば、管理費等の支払いができなくなることもある。さらに孤立死などが発生し、相続人が見つからなかったり、相続放棄をされたりすることがあれば、法的な手続きなどを経て次の区分所有者に譲渡されるまで管理費等が滞納になることもある。管理費等の督促業務は、そうした社会の変化を敏感に読み取る必要のある業務だと言ってよいだろう。
1. 当社の管理受託マンションにおける滞納率は0.4%
現在、当社が管理を受託する管理組合における管理費等の滞納率は0.4%であるという。0.4%と聞いただけでは高いのか低いのかよくわからない。国土交通省が実施する令和5年度マンション総合調査によれば、以下のような状況になっている。
- 滞納管理費がない管理組合は62.1%
- 滞納管理費等が0%超から10%である管理組合は29.2%
- 滞納管理費等が10%超である管理組合は0.5%
滞納率が0.4%とは、ちょうど学校給食の滞納や固定資産税の滞納と同率であるそうだ。マンション総合調査と比較するとかなりの低率だ。
学校給食費の徴収状況に関する調査
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1341369.htm
令和5年度 地方税滞納等額等及び徴収率
https://www.soumu.go.jp/main_content/000998633.pdf
私の記憶では、15年くらい前だろうか、滞納率を下げることがマンション会計部の目標のひとつになっていたはずだ。滞納率はどうやって下げてきたのだろうか。
「最初からこんなに低率であったわけではない。徐々に下がっていった」そうだ。
福原さんは金融機関勤務を経て、当社に入社。25年前の当時、手作業のいわばアナログ業務がほとんどで、どのマンションで管理費等の滞納があるのか、その件数、金額という基本的な情報すら、すぐに把握できない状況であったという。督促用のシステムも導入されておらず、知識を持つ人もいない、そんな状況から始めていった。
「今では当たり前になっているが、システムを使って滞納状況をすぐに確認できるようにすること、滞納者への督促履歴は俗人的にならないよう管理し、担当者間で共有できるようにすることなど、徐々に時間をかけて今の状況を構築していきました」と苦労の多い当時を懐かしそうに語る。

※枠内のデータについて
枠内期間は会社合併によるシステム統合などの都合により集計方法が異なる。
2. マンション標準管理委託契約書の「訪問督促」の問題
マンション標準管理委託契約書には、「管理費等滞納者に対する督促」として「自宅訪問」による方法がある。ひところ、消費者金融等の取り立てが社会問題になったが、あのような取り立て屋まがいのことをして、管理会社が管理費等を取り立てるという誤解をしている人もいたくらいだ。
常々、私はこの「自宅訪問」については、弁護士法72条によって禁止されている「非弁行為(※)」に該当する場合もあるのではないかと考えていた。非弁行為に該当するなら、管理会社は訪問督促をしてはならないのではないだろうか。
※ 非弁行為とは、(i)弁護士ではない者が、(ii)報酬を得る目的で、(iii)訴訟事件に加え、当事者間で既に紛争が発生している事案や、将来紛争が発生する可能性が高い(あるいはほぼ避けられないような)事案(「法律事件」)について、(iv)法律相談を行ったり、代理人として交渉を行ったりする行為(「法律事務」)を、(v)業とする(繰り返し行っている、あるいは初回であるとしても繰り返し行う予定で行う)ことをいいます。
(東京弁護士会HPより)
マンション標準管理委託契約書から抜粋
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
※「甲」は管理組合、「乙」は管理会社を指す
この点についても福原さんに尋ねてみた。
「自宅を訪問すること自体は問題ありません。しかし、個別の事例により判断は異なると思いますが、私も非弁行為に該当する可能性は極めて高いように思います」とのこと。
「非弁行為に該当しないように訪問するなら、玄関前でピンポンして、『滞納管理費があります』という事実をお伝えすることに留まってしまうため、お伺いする理由がありません」と言う。
確かにその通りだ。
3. 裁判所の判断の変化
福原さんの思い出話をさらに突っ込んで聞いてみる。昔と今で大きく異なるのは、何も当社の体制ばかりではないらしい。
「10年くらい前までは、管理費等の滞納に関する訴訟が少なく、裁判官も書記官も「管理組合」の特殊性を把握しておらず、その説明に時間を要することもありました。しかし、マンションストック数が増加したこともあってか、訴訟の数が増加し、裁判官も書記官も「管理組合の裁判」に慣れてきたように感じています」とのこと。
参考 紛争の実態。マンションではどんな訴訟が起きているか?
https://www.miraikachiken.com/report/210830_report_01
「例えば、管理組合を原告とする訴訟にかかる弁護士費用については、ひと昔前までは、原告と被告で折半するとか、そういう判決もありました。今では、マンション標準管理規約に記載がある通り『弁護士費用等も違約金として区分所有者に請求できる』ため、被告人である区分所有者の負担が認められることが多くなりました。つまり、管理組合は余計な負担なく、管理費等を回収できるのであれば、訴訟を起こすことに躊躇する必要はありません」
参考 マンション標準管理規約
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
ただし、唯一、認めてもらいにくい費用が「自治会費や町会費」だそうだ。
「自治会費の徴収に関しては、さまざまな徴収方法があります。管理組合と自治会は別の団体ですから、本来であれば自治会費は管理組合が徴収するべきものではありません。この原則の通り、自治会役員が各戸を回って徴収しているケースもあります。しかし、それでは自治会役員に負担がかかりすぎます。そこで、管理組合がいわゆる「代行徴収」をする方法をとる管理組合もあります。管理費等の引き落としの際に、自治会費をプラスして引き落とし、自治会費分を自治会に振り込む、という方法です。この場合、管理組合は代行しているだけであり、債権者ではありません。債権者はあくまでも自治会です。こうした理由で自治会費は滞納管理費の一部として認められにくいようです」
滞納管理費等の回収業務も時流とともに移り変わっているようだ。
4. 月に1000件、「区分所有者変更届」から見えてきたもの
区分所有者が変更になったときに、仲介会社やご本人から管理会社に送付されてくる「区分所有者変更届」。おおよそ月に1000件、不動産取引が多い3月には2000件に及ぶ。これをもとに、管理費等の請求を行う。この区分所有者変更届を受け付けるのが、当社ではマンション会計部である。福原さんがその課長をしていた10年程前に、ふと、届出書に記載された「変更理由」に「相続」が増えていることに気付いたという。おおよそ、1割程度は相続による変更というから驚きだ。
「高齢化社会、孤立死問題など報道されていますが、それまで実感値として感じたことはありませんでした。毎日の業務の中でそのことに気が付いた時、自分も何かしなくては、と思うようになりました」とのこと。
そこで、福原さんは社内提案制度を利用して、高齢者向けサービスの窓口となる「プレシャスライフ相談室」を立ち上げる。今では、福原さんの手を離れているが、創始者のひとりである。
「認知機能が衰えてきたが頼りになる後見人がいない、親族が死亡したが手続きがわからない、孤立死があり特殊清掃を依頼したいがどこに頼んだらいいかわからない、そんな区分所有者や管理組合からの相談を受けました。管理会社はあまり感謝されない業種と言われがちですが、この時は本当に感謝されてうれしかったですね」と話す。
区分所有者変更届の確認、ややもすると機械的な仕事に陥りがちとも思えるが、その中に深い人間ドラマを見出す力が福原さんの原動力なのだろう。
5. フロント担当者を応援したい
福原さんからマンション管理業について語ってもらう。
「フロント担当者は、日々、管理組合から多岐にわたる質問や要望を受け止めています。ですが、一人で対応することには限界があります」と始める。
「民法、区分所有法などの法律的知識、点検や修繕工事となれば建築や設備の知識が必要とされます。しかも、大規模なマンションとなれば、区分所有者に弁護士や司法書士、税理士、建築士などの専門家が必ず存在します。企業の法務部門や、建設会社に勤務する人もいます。そうした専門家が協力的な場合はよいですが、中にはフロント担当者に攻撃的に質問してくる人もいます。専門家としてのアドバイスをお願いしたいところが、そうならないこともあります」
福原さんは続ける。
「管理費等の督促業務も、知識と経験がないと立ち行きません。それを全員のフロント担当者に求めるのは無理だから、自分がいるのです。フロント担当者を応援したい。それが一番かなと思います」実に頼もしい発言である。
そんな福原さんがフロント担当者向けの研修などの際に使用しているという資料を見せてもらった。「管理費等の滞納が議題となる理事会に出席するときの心得」である。

「滞納管理費があると、理事の方々は慌ててしまい、どうしていいかわからない。そんなときはまず最初に、自分たちが当事者であるという意識を持っていただけるようにします。
次に、管理費の滞納は決して特殊なことではなく、どんなマンションにも滞納する人は必ずいるということ、どのようなマンションでも直面する問題だということをご理解いただく。そして、管理会社がすべてをやってくれると誤解されている方には、法律上、管理会社は回収業務を行うことはできないことを、はっきりとお伝えすることが大切です」
もちろん、管理会社としてお客様に寄り添うことが大前提であり、その上で、「管理費等は特定承継人に支払う義務があり(※)、法律によって守られていることなどを説明するように伝えている」そうだ。
※特定承継について
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(以下略)
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
「よくいただくのが、管理組合からの『滞納管理費の対応について法務の見解がほしい』という依頼です。しかし、管理会社の法務部や顧問弁護士は、管理組合の顧問弁護士ではありません。また、自分たちはこれからどうしたらいいか?という行動レベルのアドバイスを求めている人に、法律的見解を持って行っても解決にはつながりません。
『最初に管理規約を改正してください』
『総会を開催して法的手続きに移行することを決議してください』
こういった行動レベルのアドバイスができるのが、自分の強みであると思います」という。
実務家は強い。
6. どうなる?管理費等の滞納
ずばり、これから管理費等の滞納はどうなっていくかを聞いてみた。
「従来型の滞納、つまり、失業などによる収入減により管理費等が支払えなくなった方への対応については、すでにツールは揃っています。あとは、管理組合がどう決心するかだけです。これから増加していくのは、意思能力の衰えや病気、死亡などの理由による管理費等の滞納と考えています。これらは本人だけでは解決が難しく、親族などの周辺の人の協力が必要になる。人間関係も手続きも複雑で時間がかかる。マニュアル通りにはいかない。そういった滞納が増加していくと思います」
こうした複雑な案件もある程度は類型化していくため、それらの対応方法を管理組合に伝えていくことはこれからも必要になるだろう。福原さんにはさらにもう一肌脱いでもらいたいものだ。
福原さん、ありがとうございました。


マンション管理士、防災士。不動産会社での新築マンション販売、仲介業を経て、大和ライフネクストへ転籍。マンションフロント担当、賃貸管理担当などを経験したのち、新築管理設計や事業統括部門の責任者を歴任。一般社団法人マンション管理業協会業務法制委員会委員を務める。著書『マンションの未来は住む人で決まる』が第15回不動産協会賞を受賞。