保険料値上がり中! マンション共用部分の保険はこれからどうなる?!
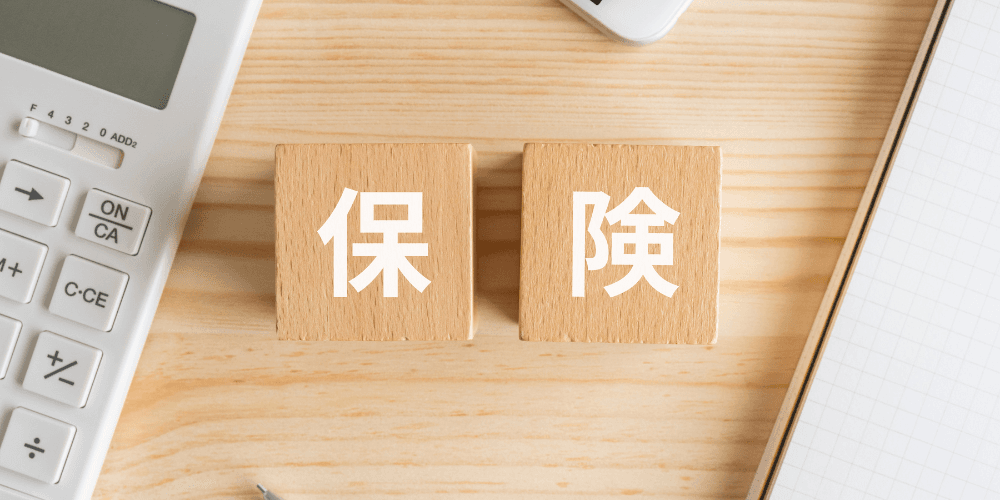
今回お話を聞くのは、マンション向けの保険を取り扱うインシュアランスエスコート部ソリューション課の松永洋一さんだ。現部署に至るまでにマンションのフロント部門の支店長、支社長を歴任してきたベテラン社員である。現場のことも保険のこともよく知っている頼もしい存在だ。
◆取材者:久保 依子 マンションみらい価値研究所 所長

多くの管理会社では一般的に「保険部」と呼ばれる部署が保険代理店業務を行っている。インシュアランスエスコート部はまさに「保険部」に該当する。
そもそも「マンションの保険」と言ってもさまざまあり、大きくは共用部分の火災保険と、専有部分の火災保険がある。前者は管理組合が加入しエントランスやエレベーター、バルコニーなどの共用部分を補償範囲とするもので、後者は各区分所有者が自身の所有している住居部分・家財を補償するために加入するものである。
インシュアランスエスコート部では、管理組合向けの共用部分を対象とした保険のほか、居住者向けの保険も取り扱う。管理会社とはいえ、商品が損害保険であるから、他の部署とは業務に必要な知識も異なる。フロント社員は管理業務主任者やマンション管理士などの資格の取得が求められるが、保険部は損害保険募集人資格に加えて、さらにその上級資格の取得が求められる。管理職ともなればそれらの取得は必須と言えるだろう。
私も「保険部に異動になると勉強するのが大変だ」という漠然としたイメージを持っている。もちろん、松永さんはあらゆる資格を一通り取得済みである。同部に異動後、かなり勉強したそうだ。
1.興味本位で最近の保険不正請求事件を聞いてみた
損害保険と言えば、近年発生した一連の不正請求問題が記憶に新しい。ずばり、あの事件はマンション管理会社にも影響を与えているのかを聞いてみた。
「マンション火災保険は、損害保険全体から見れば市場規模の小さい商品と言えます。今は直接的な影響と言えるようなことは起きていません。ただし今後は、こうした不祥事を受けてさまざまな対応がなされると思います。例えば、金融庁が代理店である管理会社に立ち入り調査に来ることも考えられます」との指摘。
企業が不祥事を起こすたび、監督官庁の当該業界への風当たりはどんどん強くなる。「金融庁」と聞くと、人気ドラマ『半沢直樹』の査察シーンを想像してしまうが、「まずは保険業法の順守状況の確認や、業務の流れなどをヒアリングするようなイメージではないか」とのこと。いずれの業界もコンプライアンスは最重要課題であることに変わりがないようだ。
なんら悪いことをしていなくても、金融庁が立ち入り調査に来るようなことがあれば、かなり緊張するだろう。そんなことを勝手に想像してドキドキする。
2.保険代理店は誰の代理?
「管理会社の保険部は誰の代理人ですか?」私が常々思っている疑問だ。
「もちろん、保険会社の代理人ですよ」とあっさり。私の質問の趣旨は次のようなものだ。
保険部は、管理会社の組織の中にある。つまり、管理組合側の立場に立つ必要があるはずだ。しかし、保険会社の代理人であるなら、保険会社側に立つことになる。例えば、マンション内で事故があって管理組合が保険金の支払いを受けたい場合に、不本意な額の保険金の支払いしか受けられないとする。「もっと頑張ってよ!」の一言を言いたいときに、一体誰を味方に交渉すればいいのか。
この疑問に彼は「自分なりの考え方」との注釈付きで次のように説明してくれた。
「保険金の支払い額に不満がある場合、保険会社側に保険金算定のもととなる事故について①事実の誤認、②技術的解釈の誤認、この2つのうち、いずれかの誤認があれば、代理店として保険会社に対して適正な評価をするよう求めることもあります。『どっちの味方』という感情論ではなく、客観的事実に基づいて意見を述べるということです」
なるほど。「どっちの味方」の議論になると利益相反だの双方代理だのという用語が飛び交うようになるが「事実の誤認の有無」ならそんなに問題にはならない。
松永さんいわく、「久保さんのように『どっちの味方だ!』と叫ぶ人、いるんですよね」と笑う。
3.お得な保険会社はありますか?
続けて失礼な質問をもうひとつ。みなさんも感じているだろうが、損害保険会社の商品は何が違うのか分かりにくい。「ずばり、この会社のこの保険がオススメ、などのお得情報はありますか?」と聞いてみた。
「マンション保険に関して言えば、保険会社間では補償内容に大きな差はないと言ってよいと思います。ただし、補償の範囲や条件等に細かな差異はあります。例えば、漏水や水濡れ事故に悩む管理組合は、その部分の補償がある保険がよいでしょうし、植栽がたくさんあってその手入れに多額の費用をかけてるようなマンションは、植栽に着目して保険を選択してもよいでしょう。最初から『この会社』と決め打ちせず、相見積を取って比較してみましょう」とのこと。
さらに、保険を使用しなかった場合に次回の保険料が割引になる制度や、最近では管理状況に着目した「管理状況割引」や「メンテナンス割引」といった割引が使える商品も出てきているという。
「お得な会社を選ぶ、ということではなく、自分にあった会社を選ぶ、ということですね!」
【マンション保険比較のポイント】
①施設の屋根や外壁から入る雨・雪等による雨水漏水事故が補償対象となっているか?
②植栽への強風等による単独損害が補償対象かどうか?(建物と一緒の被害が条件となるかどうか)
③水ぬれ事故の原因調査費用にどれくらい備えるか?(回数や年間上限額の比較)
4.値上がりする保険料、保険会社が保険を引き受けない事態になるのでは?
2025年1月、連日のように報道されていたロサンゼルスの大規模火災では、「異常気象の影響で火災が起きれば甚大な被害が出ることが予想されていたため、住宅向けの火災保険への加入を損害保険会社が拒絶し、多くの被災者が保険金を受け取れない事態になっている」と一部メディアで報道されて話題になっている。陰謀論まで囁かれているらしい。
一方、日本でも築年数が経過しているマンションでは、暴騰とも言ってもよいくらいの保険料の値上がりがある。
「保険会社も商売ですから、高経年のマンションでは採算が合わないとなれば、突然、火災保険を引き受けません、や~めた!なんていうことになりませんか?」と聞いてみた。
「保険会社としては、『支払う保険金の総額+制度維持のコスト』が『契約者が支払う保険料の総額』を超えると、保険は成立しないことになります。
例えば、2019年は特に台風の上陸や接近、集中豪雨が多発した年です。その被害を補償する水災保険は前年の2倍以上の支払いが生じています。これをカバーするためには契約者が支払う保険料を値上げせざるを得ません。異常気象の原因は地球温暖化であることは明らかです。災害が減ることはないでしょうから『どんどん値上げする』という傾向はこれからも続くと思います。ただ、突然保険の引き受けを『や~めた!』というのは社会的影響が大きすぎますから、限界が来る前に、例えば契約期間を短くするとか、補償の内容を減らすとか、自己負担額を上げるとか、そういう方向に行くのではないでしょうか」
なるほど。キャベツが高騰すると半分や4分の1に割ったものが店頭に並ぶのと一緒ということか。

5.南海トラフ地震や首都圏直下型地震が起きても、保険金は支払われるのか?
多額の保険金の支払いといえば、地震保険だ。南海トラフ地震や首都圏直下型地震が発生したら、何兆円にもなるのか、見当もつかない。保険会社が破綻してしまっては、支払いすら受けられないのではないか?そんな不安もぶつけてみた。
「地震保険は、大災害時においても保険金の支払いが確実に行われるよう、政府が再保険を引き受けることによってバックアップされています。この図で説明しましょう。
1回の地震等によって政府と損害保険会社が支払う保険金総額に限度額が設けられています。これは総支払限度額と呼ばれ、現在は12兆円です。まず、1回の地震等により支払われる保険金の額が1,827億円に達するまで(1stレイヤー)は民間が負担します。次に、1,827億円を超え3,807億円に達するまで(2ndレイヤー) は政府・民間が50%ずつ負担します。さらに、3,807億円を超える部分(3rdレイヤー)については政府がその大半(約99.5%)を負担します。
ちなみに東日本大震災に対しては、発生から12年後の2023年3月までに1兆2,891億円が保険金として支払われています」

東日本大震災で1兆円超えだとすると、12兆円までまだ相当にキャパシティがある。素人的にはなんとなく間に合うような気がしてきた。
なお、地震保険の付帯率は全国で69.7%、当社の受託管理組合では88.2%であるという。当社が管理するマンションの管理組合は防災への意識が高いということだろうか。

6.マンションの保険はこれからどうなっていくと思いますか?
ずばり、松永さんにこれからのマンション保険はどうなっていくのか聞いてみた。
「マンション管理に関わる方なら、誰もが見慣れたグラフだと思うのですが、国土交通省が公表しているマンションストック数の推移を示したグラフです」そう言いながらグラフを示した。総ストック数が700万戸を超えているというアレである。

「これを90度回転させて黄色い棒グラフ部分だけに着目してみます。どこかで見たことがあるグラフに似ていませんか?」

色々考えたが答えは出ず、松永さんに解答を教えてもらう。答えは「人口ピラミッド」だ。確かにちょっと似ている。

「マンション保険もある意味、人口減少で破綻しかけていると言われている日本の年金制度と考え方は同じようなことが起きているのです。仕組みとしては、築年数の経過したマンションの保険金の支払いが増える、それを事故の起きない新しいマンションが支えている。もちろん同じ保険料だと不公平なので、築年別料率という体系になっています。グラフの通り、新築供給マンションが減少し、バブル期前後の大量供給時代のマンションが、いわば団塊の世代のように増加しています。災害の増加や工事費の高騰も考慮すると、残念ながら、保険金支払額は現状では減る見通しが立ちません。今の補償を維持したままでは、保険料を上げざるを得ない状況は続くと思います。
ただし、火災保険の高騰に加え、金融審議会においても、保険料率の設定方法の見直しや商品開発の柔軟性などが議論されています。政策・商品改良等なにがしかの改善が図られる可能性も十分にあると思います。
損害保険が担う大きな損害・被害への備え、貯えで賄いきれない被害への備えとしての役割は重要であることから、私たちも保険の重要性をこれからもお伝えし続けていたきいと思います」
今回は、私が保険制度に抱いていた疑問をだいぶ解消することができた。松永さん、ありがとうございました。

【4月開催セミナー】
速報!ついに法案提出 改正区分所有法 ~改正法の条文をもとに、徹底解説!~
>セミナー詳細・お申し込み

マンション管理士、防災士。株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)での新築マンション販売、不動産仲介業を経て、大和ライフネクストへ転籍。マンション事業本部事業統括部長として主にコンプライアンス部門を統括する傍ら、一般社団法人マンション管理業協会業務法制委員会委員を務める。著書『マンションの未来は住む人で決まる』が第15回不動産協会賞を受賞。







